 まやまやさん
まやまやさんこの間相談した開業して個人事業主になると、扶養に入れなくなるんですか?
まやまさんついに週20時間以上の仕事を辞めて、それまで副業だった仕事や業務委託の仕事でフリーランスになったんでしたね!今は雇用保険の失業給付を受給中で、いったん国民健康保険にしたんだよな。
給付が終わるまえに判断しなければならない事がいくつかあります。先ずは配偶者の扶養に入るかどうかですね。ちょっと整理してます。
配偶者の扶養に入るかどうか?
個人事業主で①所得税法上の扶養にはいる
配偶者(納税者)は所得税や住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。
配偶者控除 所得合計額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
- 失業等給付は、控除対象配偶者の判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。
配偶者特別控除 所得合計額が48万円超〜133万円以下
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
事業専従者を除けば、雇用形態は控除の要件では無いので個人事業主も対象です。その場合は、合計所得金額つまり(収入金額-必要経費等)が48万以下であれば配偶者控除、133万以下であれば配偶者特別控除が受けれれます。また失業給付は合計所得金額には含まれません、
個人事業主で社会保険上の扶養にはいる(協会けんぽの場合)
配偶者(被保険者)の被扶養者として国民年金の保険料の納税義務がなくなる
配偶者(被保険者)の被扶養者として健康保険に加入できる
自分で社会保険に加入している時と比較すると、将来受給できる厚生年金額が下がる可能性があります。
被扶養者の範囲
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 - 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。- 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
- 上記配偶者が亡くなった後における父母および子
収入の基準
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※2 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります
夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出してください。
配偶者が被用者保険の被保険者の場合
被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。
配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
手続き時期・場所および提出方法
被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
被扶養者の認定
提出時期:事実発生から5日以内
提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
社会保険の被扶養者要件では、配偶者(被保険者)の年間収入に制限はなく、被扶養者となる個人事業主本人の年間収入が130万円未満かどうか、という点がポイントとなります。130万円以上であった場合には社会保険の扶養に入ることができなくなってしまうため、個人事業主はこの「130万円の壁」に注意する必要があります。なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。(出展:freee青色申告の基礎知識 https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/#content3-2)
社会保険の扶養の場合は、失業等給付も収入に含まれる点が要注意です。また給与所得者の扶養控除等申告書に「令和〇年の所得の見積額」は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈のワンステップがあるところが所得税と異なるので、念のため確認は必要かもしれません。後は提出期限が5日以内です。
個人事業主で扶養に入らず働く
ここまでの説明から判るように、
①所得税法上では配偶者(納税者)が配偶者控除または配偶者特別控除が受けられなくなります。
扶養の場合の課税所得(所得-控除)の控除による、ご主人の所得税の軽減の効果は無くなります。目安としては、控除額x税率(現在が参考値)になります。
②社会保険の配偶者(被保険者)の被扶養者ではないので、ご本人の健康保険と国民年金の負担が必要になります。この負担した社会保険料はご自身の確定申告の際の社会保険料控除には反映されます。
以上の事から、雇用保険の失業給付が終わる前に準備すべきことを整理すると
- 前職の給与収入と副業の収入と経費1)
- 源泉徴収票や領収書等の整理
- フリーランスになってからの仕事による収入と経費2)
- 同じく各種書類の整理
- 税務署に事前相談
- 開業届を出す前の収入・支出は事業所得として扱うことは可能かどうか?
- 青色申告する場合の、開業費に含められる項目の確認、特別控除65万に会計ソフトは必要か?
- 会計ソフトの選定
- 費用、使いやすさ
- 不明点を質問できるかどうか?
- step1とstep2の情報から、青色申告する場合としない場合の二通りで年間の所得を見積もる。
- 扶養に入らない場合の保険料と国民年金の負担額を見積もる。
二通りで年間の所得により、扶養扱いになるかどうかを確認する。特に社会保険は協会けんぽに確認した方が良いかもしれない。
二通りで扶養扱いになるかどうかも含めてのトータルの収入に対する税と社会保険の負担額を引いた残りの手取り金額を比較する。もし際どい場合は、仕事の量を減らして扶養に入る場合と増やして手取りを増やす場合もシミュレーションして判断する。
扶養を希望する場合は、提出期限が5日以内に提出する。
収入要件確認のための書類(日本年金機構HPより)
1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者※
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者の適用は受けられないため、収入確認の証明書類が必要です。
被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要となります。
(2)(1)以外の者
ア.退職したことにより収入要件を満たす場合
退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
イ.雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し
ウ.年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
エ.自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合※
直近の確定申告書の写し
※自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。
オ.上記イ~エ以外に他の収入がある場合
- 上記イ~エに応じた書類
- 課税(非課税)証明書
カ.上記ア~オ以外
課税(非課税)証明書
思いつくところまとめました。また追加修正点があれば更新しますね。









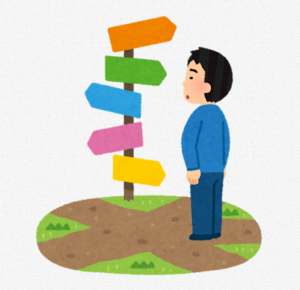
コメント